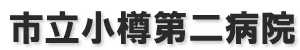 |
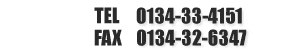 |
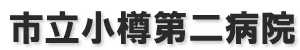 |
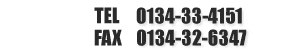 |
〈一般撮影〉 放射線関連の検査の中では最も多く行われている検査です。 胸部・腹部や頭・脊椎・手・足などの骨の撮影をします。 当院では直接フィルムに写す代わりに、イメージングプレートと呼ばれる記録媒体を使用したCR(Computed Radiography)が導入され、検査部位に合わせたより良い画像を提供しています。 撮影される患者様は、各診察科において渡された撮影伝票を放射線科受付に出して下さい。 また、病室での撮影にはポータブル撮影装置を使用しています。 |
|||||
〈MRI検査〉 MRIとはMagnetic Resonance Imagingの略で磁気共鳴画像とも呼ばれます。 特徴として磁力と電磁波を使い各臓器・骨・筋肉など体のあらゆる方向の断面画像が得られたり、血液の流れを画像化し、動脈瘤や血管の狭窄などを調べることができます。 注意しなければいけないのは、検査を受ける方にいろいろ制限があることです。 特に心臓ペースメーカーを体内に埋め込まれている方は、MRI検査はできません。 そのほかにも手術などで金属類が体内に埋め込まれている方は、検査の妨げになることがありますので主治医とご相談してください。 検査中は大きな音がしますが痛みなどはありません。 |
|||||
〈血管造影検査〉 血管造影とは、上肢またはソケイ部の血管から細い管(カテーテル)を挿入し造影剤を注入して、目的の臓器の血管を連続的にX線撮影する検査のことです。 当院では主に心臓血管と脳血管の検査が行われ、血管の狭窄や瘤、腫瘍等の情報をリアルタイムに得ることができます。 最近では検査のみならず、狭窄血管の拡張や動脈瘤の塞栓など手術に代わる治療法として応用範囲が広がっています。 |
|||||
 |
 |
||||
〈核医学検査〉
核医学検査は、単純X線、CTスキャン、超音波(エコ-)、MRIなどと同様の画像診断の一つで、病院によってはアイソトープ検査あるいはRI検査などとも呼ばれています。微量の放射線を出す放射性医薬品を患者様に投与して、その体内での分布を外部から画像や数値として捉え、形態、病態の把握、治療効果判定に役立てる検査方法です。 検査は、多くの場合放射性医薬品を静脈注射し、ガンマカメラという装置の下に寝ているだけであり、患者様への負担は大変少なく、1回の検査はおおよそ5分から1時間以内に終了します。 核医学検査における放射線の影響は、普通の生活で人が自然界から受ける年間放射線量と同程度で、それによってただちにデメリットを受けるような量ではありません。 |
|||||
〈CT検査〉 CT検査とは、体の周りからX線を照射して、人体を透過してきたX線を検出し、体の中の様子を画像化する検査です。 検査は、ベッドに横になって行い、検査部位により呼吸を止めて行うことがあります。 検査部位によりヘアピン・ネックレス・イヤリング・義歯などを外していただく場合があります。 検査によっては造影剤という薬を注射しながら行う場合があります。 |
|||||
Copyright(C)2007 Municipal 2nd Hospital in Otaru All Rights Reserved. |